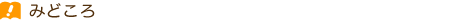
スティーブン・スピルバーグ氏が映画化した『シンドラーのリスト』を知っている方はピンとくるかもしれません。
本書は、第二次世界大戦のナチス・ドイツ支配下で、1200人のユダヤ人を守った実業家オスカー・シンドラーのユダヤ人リストの中、最年少のひとり、当時10代の少年だったレオン・レイソンの回顧録であり貴重な証言です。
ポーランドの村で平穏な暮らしをしていた5人兄弟の末っ子、レオンの人生が一変したのは1939年。ドイツのポーランド侵攻によってゲットーへ強制的に入れられ、苦しみの日々がはじまったとき、レオンはまだ10歳でした。
原題は「The boy on the wooden box」。父兄とともにシンドラー工場で働くレオン少年は、木箱の上に立たないと機械のスイッチに手が届かないくらい小柄でした。そんな貧相な少年を、シンドラーはナチスに対して「熟練の技術工」と言い張り、従業員リストに加えます。莫大な賄賂を送り、ナチス親衛隊との友好な関係、社交術を駆使してシンドラーが守った人数は1200人。多いと思うか少ないと思うかは人それぞれだと思いますが、シンドラーはユダヤ人従業員をナチスに引き渡すことをさせなかった。あの時代、相当危険なことであったのは間違いありません。
オスカー・シンドラーについてはこれまで様々な評価がされ、ナチスの日和見主義者、策略家など、いい評価だけではないそうです。
でも本書はそんなシンドラーを間近で見、命を救われた当事者として、大事なことを教えてくれます。それはあの異常事態のなかで、「正気を保つ」のがどういうことか、ということ。ただユダヤ人というだけで「虐げてもいい存在」としてあっという間に黙殺され、周囲からは見て見ぬふりをされていく。親衛隊の隊長は気まぐれで射殺し、カードゲームのように殺した数を数える。その中でシンドラーは、ユダヤ人一人ひとりに興味と関心をもって向き合いました。
レオンは証言しています。「ナチスにとって私はユダヤ人のひとりでしかなく、名前は意味を持たないという事実に、私はすっかり慣れてしまっていた。けれど、シンドラーは違った。彼はあきらかに、私たち一人ひとりが誰であるかを知ろうとした。」「こちらの目をのぞきこむ彼の目には、ナチスの虚ろな凝視とはまるで違う、本物の関心があり、ユーモアの片鱗さえも感じられた」と。
本書は、過酷なゲットーや収容所で、死のすぐ隣にありながら幸運にも生き抜いたレオン少年の体験記であり、威厳があった父親がナチスによって打ちのめされ変わってしまった夜や、目の前で最愛の兄がなすすべもなく連れ去られた「全身の血が逆流するような」場面など、忘れがたい瞬間が記録されています。命がなくならなかったのは、レオン少年が必死で賢く勇気をもって動いた結果の、奇跡の幸運であったことが、読めばわかります。
今、本書を読むとき、私たちは忘れかけていた戦争の狂気を自分のことのように感じることができるでしょう。レオン少年が自分だったら。自分の子どもだったら。私たちは家族として生き抜くことができたでしょうか。
最悪の状況の中でも、レオン少年は家族からの愛情を感じていたからこそ、自分の命を価値あるものだと信じることができたと言っています。
「ヘイト」すなわち憎しみや嫌悪という感情は、個々の人間同士ならば当たり前でも、集団になるとおそろしい狂気を生み出します。憎む集団が生まれたとき、私たちはどちらの集団にも属しうるのです。憎む方にも、憎まれる方にも。それを、本書を通じてレオン少年に心を寄せ、想像してみませんか。
戦争が終わったとき15、6歳だったレオン少年。そこから先の人生のほうがずっと長くとも、決して消えない時間が刻まれました。その測りかねる重さを、静謐な口調で、少年の素朴な驚きや関心や恐怖で、ありのままに綴った記録。当時のレオン少年と同じ年頃の10代の子どもたちにぜひ読んでほしい本です。
(大和田佳世 絵本ナビライター)

スピルバーグの感動的な映画「シンドラーのリスト」に登場するユダヤ少年による回想録。死と隣り合わせで生きた残酷な時代、シンドラーの勇気と人間性。中学生から読める「真実の記録」。
|