|
|

幼い日、本のぎっしりつまった古い小部屋でひねもす読みふけった本の思い出――それは幻想ゆたかな現代のおとぎ話を生みださせる母胎となりました。ユーモアと風刺に富んだ楽しいファンタジー27編。
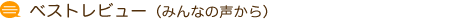
1971年:石井桃子訳で刊行。原書は1955年刊行。作者が70歳以降に、自分の作品の中から27篇を選んだ童話集。
作者の前書き:生い立ちや、子ども時代の読書環境など、から始まり、童話27篇、後書きに訳者の解説や翻訳時の工夫などが語られる。子どもの楽しめるいいお話に生涯をささげた女性二人の、真心のこもった本。
童話は創作もあれば、何かの昔話を下敷きにしたようなものもある。
悲しいお話、感動的なお話、社会を皮肉ったお話、ちょっとしたお話、けっこう長いお話、詩のようなお話…など、いろいろな話がいっぺんに楽しめる。昔の外国の様子が、レトロな挿絵で表され、物語の情景を想像する助けになる。
どれも美しい情景や、人々の心の動きが生き生きと感じられ、読み応えのある物語ばかりだ。
印象に残ったのは「十円ぶん」というお話。
十円玉を拾った少年が、いろいろな冒険をするというお話。原書は外国で出版されたので、通貨の単位や価値などが日本とは違うが、翻訳者が日本の1970年代の子ども達に、身近に感じられてよく理解できるように「十円」とした、という。
ガチャガチャに入れて、おもちゃを1つ買えるくらいの金額。
駄菓子屋でお菓子が1つか2つか、買えるくらいの金額。
電車で1駅か2駅くらい、行かれる金額。
正確にはわからないが、おそらくそのくらいのお金。お小遣いを名いっぱい楽しく使うために、知恵を絞った子ども時代。
今は生活費の工面や、会社の経理などで無駄が出ないように知恵を絞っている。
お金の話は、なかなか楽しい童話になりにくい気がしたが、さにあらず。読者が追体験しやすい、身近な物語になっていた。
石井桃子訳の、独特の言葉のセンスが楽しく、妙に懐かしい。
ママ、と言わず、おっかさん。
日本の昔話でも語るような口調で、ちょっと外国のユーモアもたっぷり、生きる知恵や苦しみ、喜びも悲しみもたっぷり入った、濃厚な物語を楽しめる。今、こういう昔気質の、美しい日本語は貴重だ。
やや大人向きかもしれない。
(渡”邉恵’里’さん 40代・その他の方 )
|