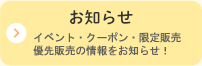●作家が表現したいことを表現した
─── 出版されて初めて、本を通じて知ること、伝わってくる風景があります。『京劇がきえた日』(中国/姚紅<ヤオ ホン>作)は日常のなかに文化が根付いていた様子、壊れていく情景が伝わってきます。
姚紅さんオリジナルの、これだけ素敵な1冊ができたということは、実は大変なことだったんですね。中国は出版の形態が、日韓とまったく違う。いわゆるフリーの絵本作家は存在しないんです。出版社はだいたい国営で、画家は編集者として仕事をしている場合が多い。そして出版が決まった文章に挿絵をつけるという形です。出版には審査も必要です。日韓の出版環境は近かったけれど、中国では、絵描きが自ら発想しダミーを作って出版社に持ち込むことは習慣としてなかった。自作のオリジナルを作ることが、日本で考えるより何倍も大変なことだったんです。その点で、和歌山静子さんの役割は大きかったと思います。和歌山さんは、ダミーの作り方から一生懸命伝えていました。『京劇がきえた日』の女の子は、姚紅さんのお母様がモデルなんですよね。お母様から聞いたお話がベースになっているそうです。でも中国は文化大革命もあったし、この時代のことがわからないので資料集めが大変で。京劇の衣装も、衣装コレクターの方のところへ行って一所懸命取材したんですって。で、あまりの熱心さから、衣装を盗むんじゃないか、と疑われて(笑)と面白いお話もされていました。私たちは、中国の方が京劇の衣装を描けるのは当たり前みたいに思うけど、大学の学生さんの協力でインターネットも駆使して資料集めして…苦労されたそうですよ。でもやっぱり…中国の方でしか描けないすばらしい絵ですよね。女の子の有様、京劇の役者さんの風情も。日本人が絶対描けない絵。姚紅さんは、プロジェクトのおかげで、この絵本をつくることができたとおっしゃっていました。
─── 12冊、これから順次出版されていくわけですが…。
ふつう、出版社が12冊をこんなテーマでどんな作家に描いてもらってとシリーズで企画を組みますよね。でも今回はまったく逆。12人の作家がそれぞれに作りたいものを作った。だから12冊集まって、どうなるのかなあとも思っていたんですけれど…不思議なことに、絶妙な、有機的な関係ができあがってくるという予感があるんです。たとえば『京劇がきえた日』には1937年という年代が出てきますね。『街のおもいで』(中国/蔡皋 作)も年代がはっきりしている。両方ドキュメントなんです。『さくら』(日本/田畑精一 作)もご自分の生い立ちを描いたもので割合年代がはっきりしてる。そうすると作品の時間が重なってくるんです。そして私が描いた『へいわって どんなこと?』や、『ぼくのこえがきこえますか』(日本/田島征三 作)のように死者の目から見る抽象世界のような作品が加わることによって、12冊がひとかたまりになって立ち上がってきて、雄弁に語りだすというか…。おそらく作品が出来上がってくれば出来上がってくるほどひとつのモニュメント的なハーモニーが奏でられていくような…すごく期待する気持ちがあります。12冊そろったとき全体から新しい違うものが見えてくるかもしれない。そこからまた、やれることがあるんじゃないかな、と。
●大人と子どもを対等にする、絵本の力
─── 絵本をとおして子どもと大人はどんなふうに触れ合えるか、浜田さんはどのようにお考えですか。
私、絵本って大人と子どもを平等にするような気がするんです。大人が、声と言葉で読んであげて、子どもがそれを耳にして、本に向き合う。でもその絵本の世界を受け止め、絵本の楽しさのなかで遊ぶのは…大人でも子どもでも一人の感情であり、一人で絵本と向き合う感覚だと思うんです。読んでもらうのは大人に読んでもらったとしても、感じとるのは、子どもが直に感じとっている。
これってすごいことで。誰か大人に保護されて、それを受け止めるんじゃない。他のあらゆることが子どもは大人に保護されてのことなんだけど、絵本の世界を受け止めるというのは、もう、ダイレクトに子どもが独自でやっていることじゃないかと。だからこそ大人にとっては、自分が受け止めたことと、子どもが受け止めたことが、交流できると。お母さんたちは、子どもが受け止めたものからまた大きな、自分は気づかない、いろんなものを受け止められますよね。大人が子どもを導いてあげるんじゃなく、一緒に、絵本という「場」に向かい合う。
なぜそう思うかというと、大人になってからの「子どものときの読書の思い出」にふれたときに不思議に感じることがあったんですね。母校のイラストレーションの講師として、毎年、20歳や21歳の若者に授業の中でよく絵本を読むんですけど、そうすると子ども時代の絵本体験の話がいっぱい出てくるの。そのときの記憶がねえ、なぜか「場面」の記憶になってる。お母さんがひざにのせてくれてエプロンが冷たかったとか、読んでたら弟がバタバタしてたとか。私自身もそう。保育園で先生が、どこかから本を出してきてお昼寝の前に読んでくれたとか。本だけの記憶じゃなく、その周りの記憶がそっくりある。
そういう「場面の記憶」を語る若者たちの顔がやわらかくてやさしい顔で。みんな嬉しい記憶なんですね。愛されていた記憶。それと同時に、読んでくれた大人と対等に絵本を遠足した、旅した、受け止めたというか…、そのことにつながるんじゃないかなと。もしかすると絵本って、まだまだ知りえない、ものすごい力があるような気がするんですよね。このごろ、そんな思いがしてなりません。
─── 私も絵本ナビ読者のお母さん方も、戦争を知らない世代です。「せんそう」「へいわ」という言葉や、子どもの受け止め方への戸惑いがあるかもしれません。『へいわって どんなこと?』をどんなふうに子どもたちと一緒に読んだらいいでしょうか。
 難しいですよね、平和の発信ってね。たとえばパレスチナやアフガニスタンの子どもが見ると、「おなかがすいたら だれでもごはんがたべられる」ということがとてつもなく幸せで、日常じゃないと受け取ると思うけど、日本の子には当たり前のことなので。え、なに? ごはん、いつもお母さんが食べろ食べろって言ってるとか。「ともだちといっしょに べんきょうだってできる」… 学校行きたくないのに、行け行けって言われてる。「あさまで ぐっすりねむれる」… どれも日常なんですね。日常って、とても当たり前で、すーっと通りすぎてしまう。
難しいですよね、平和の発信ってね。たとえばパレスチナやアフガニスタンの子どもが見ると、「おなかがすいたら だれでもごはんがたべられる」ということがとてつもなく幸せで、日常じゃないと受け取ると思うけど、日本の子には当たり前のことなので。え、なに? ごはん、いつもお母さんが食べろ食べろって言ってるとか。「ともだちといっしょに べんきょうだってできる」… 学校行きたくないのに、行け行けって言われてる。「あさまで ぐっすりねむれる」… どれも日常なんですね。日常って、とても当たり前で、すーっと通りすぎてしまう。
でも日常の場というところからは立ち位置をずらしたくなかった。子どもの視点で描きたかった。最後に「ぼく」が出てきますが、ナレーターは「ぼく」。子どもなんです。だから子どもの言葉で、子どもの立場から言う。制作途中で試行錯誤しても、最後の場面は一貫して変わらなくて、「へいわって ぼくがうまれて よかったっていうこと」「きみがうまれて よかったっていうこと」「そしてね、きみとぼくはともだちになれるっていうこと」がいちばんの平和なことだ、と。
 じゃあ、ご飯を食べるとか勉強するとかを、どうしたら読者の方たちに、あぁ、これは本当にすごいことなんだと思ってもらうか。そのために戦争の場面が必要なんじゃないかと。それで戦争の場面を入れることにしたわけです。でもほとんどが日常的な場面で構成されているので、その一場面からお話が広がっていったらいいなあと。
じゃあ、ご飯を食べるとか勉強するとかを、どうしたら読者の方たちに、あぁ、これは本当にすごいことなんだと思ってもらうか。そのために戦争の場面が必要なんじゃないかと。それで戦争の場面を入れることにしたわけです。でもほとんどが日常的な場面で構成されているので、その一場面からお話が広がっていったらいいなあと。
たとえば「おなかがすいたら だれでもごはんがたべられる」場面、いろんな国のいろんな人たちが一緒に食べてるんだけど、何を食べてるんだろうとか、みんないっぱい食べられるのかなあ、でも世界には食べられない人もいるんだよね、とか。食べられない人がいるとしたらなぜだろう、じゃあ自分たちはふだんの生活でどうしたらいいんだろうとか。決して平和って、小さな絵本でとらえきれるようなものではない。一つの扉を「とん、とん」と叩く、そんなきっかけになればいいなあと思います。
─── たとえば「いやなことは いやだって、ひとりでもいけんがいえる」とはどういうことか、と考えるだけでも、幼稚園や小学校での日常の経験と結びついて、だんだんほかのことも見えてくる。広がっていきますね。絵本ナビでも、みなさん読んだらきっと反応を寄せてくださるので楽しみですね。
そうですねえ。制作中苦労したとか、いろんな意見があったのは、作るまでのことなので。この絵本は存分にそれぞれ楽しんでくだされば嬉しい。肩肘はらずにどうぞ読んでみてください。『へいわって どんなこと?』を通じて、子どもたちとお話が弾んだら、もうそれ以上の喜びはありません。
─── ありがとうございました。

<編集後記>
この日は震災から二週間。まだ落ち着かない中での取材となりましたが、実際にお会いした浜田桂子さんは凛として「いのち」について「へいわ」について丁寧に熱く語ってくださいました。真っ直ぐ前を見据える様なその姿に、「今するべきこと」を考えていく上で個人的にも大きく影響を受けたことを覚えています。とても貴重で大切な時間を過ごさせていただきました。
(編集協力:大和田佳世)











 【絵本ナビ厳選】特別な絵本・児童書セット
【絵本ナビ厳選】特別な絵本・児童書セット