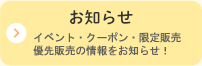●リアリティとファンタジーの融合
─── 画家であると同時にリトグラフ職人でありブックデザイナーでもあったことはうかがいましたが、絵をひとつひとつ見ていくと、ファンタジーの世界と、植物性や神話や象徴性に忠実な部分が融合しているのがおもしろいですね。たとえば『ふゆのはなし』(福音館書店)には白雪姫と7人の小人が出てきますし。

<<宴>>
廣川:『ふゆのはなし』の3人の小人は、『白雪姫』の7人の小人と、いとこ同士(笑)。グリム童話からインスピレーションを得つつ新しいふくらみをもって別の物語に昇華させていますね。
佐々木:絵本にはギリシャ神話の場面も登場します。『アルプスの花物語』(童話屋=絶版)のなかでギリシャ神話の美少年アドニス(ゼウスの怒りをかって殺される)がモチーフの絵では、アドニスの埋葬シーンもあり、死というものもおそれずに描いている。
ふつうは子どもたちに、死は伝えにくいものです。でも、彼は生と死の変化を見つめて描きました。『バッタさんのきせつ』では、昼と夜の変化が描かれています。
人生はきれいでハッピーなことばかりじゃない。それを、子どもたちは本能的にわかっています。お母さんのほんの一言に傷ついたり、あるいは災難や、津波のような大災害を経験したりもする。
子どもにこそ、クライドルフの絵にぜひ触れてほしい。絵本を見ると、ああ自分だけじゃないんだと安心するし、また「こういう残酷なことも起きるんだ」と受け入れられる。昔話も同じです。かえって、受け入れられないのは、大人の方じゃないかしら。
─── 展覧会は、子どもも見られますか。

▲小さなテーブルとイスがあって、
絵本が読めるコーナーも。廣川:もちろんです。展覧会場に子ども用の小さなテーブルとイスがあるので、そこでクライドルフの絵本(見本)を読むことができるようにもなっています。来館のお子さまには先着2500名まで、10ページほどの小さな子どもガイド「ファンタジーワークブック」をお配りしています。ひらがなでルビを振ってクライドルフの説明をしたり、クイズや塗り絵のページ、スタンプを押すページもありますよ。
美術館なので静かに見ていただきたい、会場では鉛筆を使ってほしい、などいくつかお願いごとはありますが、お子さまにも楽しく過ごしていただけるようにと工夫しました。
─── 翻訳や展示解説の上でのご苦労はありましたか。
ケーニッヒ:植物名の翻訳が難しかったですね。日本語にもない名前だったり、展覧会場内では英語の名前も表示もしているのですが英語でなんというのかわからなかったり。スイス人が植物に名前をつけるときによく動物の名前を当てたりするので、外国語に訳そうとするとわかりにくいのです。
佐々木:私も植物図鑑を見ながら翻訳しました。正確な名前を書かないと、彼がせっかく本当の学名を使って書いているんだから、と思って(笑)。彼の絵本の特色は、単なるファンタジーではなく、現実をふまえたファンタジー。ふつうは、ファンタジーかリアリティかどっちかになってしまうでしょう。
「ネコヤナギがねこになる」という文章(『花のメルヘン』より)には、翻訳に困りましたね。絵を見ると、ほんとに枝から下におりたら「猫」になってるんですよ(笑)。

<<はじめの花>>
─── ほんとだ!…そしてこちらの毛虫もすごいですよね(笑)。
廣川:模様がきれいなので、おしゃれな感じの毛虫さんに見えますよね。小さいサイズの絵に、細密に描いて彩色していますよねえ(『花を棲みかに』童話屋=絶版)。
服にトゲがたくさんある花の精をみると、この花は茎にとげがいっぱいある植物なんだなとわかりますし、「あ、こんなところに!」と何回見ても新しい発見があります(笑)。

<<毛虫のダンス>>
─── 「小さな生き物の世界は私にとって、大きな世界と同じくらい美しく大切だった」とクライドルフは語っていますね。子どもにとっても、実感できることのような気がします。たとえば『バッタさんのきせつ』はどんなふうに読んだらいいでしょうか。
佐々木:彼の絵本は、まず絵ありき、なんです。先に絵ができて、そこから自然に物語が生まれています。だから、子どもたちは無理して言葉を読まなくても、絵をみて、自分でお話を考えてくれればいいなと思います。きっと自分でも絵から色々発見をするでしょう。
もし聞かれたら、お母さんやお父さんが説明してあげればいい。たとえば<<あらし>>の場面でこれなあに、と聞かれたら、夕立がきたので、バッタさんたちがぬれないように、葉っぱをさして走っているのよ、というように。子どもたちがじっと絵を見ている間は、じゃましないで、そっとしておいてあげたいですね。
クライドルフの絵は、一級の芸術品でもありますね。それを絵本という形でも見られるのだから、味わってほしいものです。
─── ありがとうございました。

▲身を乗り出して…楽しいお話をたくさん聞かせていただきました!
Bunkamuraザ・ミュージアム「スイスの絵本画家 クライドルフの世界」開催中!
【2012/6/19(火)−7/29(日)】詳細はこちら>>>
<<宴>> 『ふゆのはなし』より 1924年以前 ベルン美術館
<<はじめの花>> 『花のメルヘン』より 1898年 ヴィンタートゥール美術館
Kunstmuseum Winterthur. Deponiert von der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Bundesamt für Kultur, Bern 1904
<<毛虫のダンス>> 『花を棲みかに』より 1926年以前 ベルン美術館
(c)ProLitteris,Zürich
【取材を終えて】
クライドルフの絵本は、日本では未翻訳のもの、絶版のものも何冊かあります。このたび『バッタさんのきせつ』が初出版されたように、人気次第では今後またクライドルフの絵本がもっと日本で手にとれるようになるかもしれませんね。
展覧会は郡山市立美術館(2012年8/4-9/17)、富山県立近代美術館(2012年11/23-12/27)、横浜そごう美術館(2013年1/30-2/24)を巡回します。お近くの方、ぜひ足を運んでみてください。


▲たくさんの素敵なグッズが生まれています!
(Bunkamuraザ・ミュージアム内、ミュージアムショップ)
(編集協力:大和田佳世)









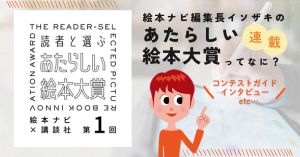
 【絵本ナビショッピング】土日・祝日も発送♪
【絵本ナビショッピング】土日・祝日も発送♪