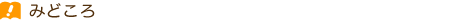
1942年、初夏。
戦争がいよいよ激しくなっていくちょっと前のこと。
家のすぐそばの表通りに、「タスケ靴店」ができた。わたしは毎日ガラス戸に顔をくっつけて、中をのぞくようになった。タスケさんは背中をまるめて、靴をカナヅチでトントンたたいたり、ぼーっと火をつけて何かをあぶったり…。ずっと見つめていると、あるとき「おいで」といってタスケさんがガラス戸をあけてくれました。それからわたしは毎日おやつのあと靴屋さんに行くようになりました。
「今は材料の革がないし、靴をあつらえるなんて贅沢は許されないしなあ。でも、こう見えても、腕はたしかなんだぞ」
そういって、ひょろ長い体にぶあついめがねをかけた靴屋のタスケさんは、いつも古びた靴を直していましたが…。
あるときわたしのねがいがかない、タスケさんにあたらしい靴を作ってもらえることになります。
大好きだった靴屋のお兄さんと、小さい女の子の物語。
かかと ととと
ととと かかと
モノクロの鉛筆画の中から、わたしのあこがれの赤い革靴が、ふしぎなリズムと共にあざやかに目にとびこんできます。
戦争の日々の中のユーモアとつつましやかなよろこび。戦争の哀しさと、女の子の胸に芽生えたときめきのあかしの赤い靴…。
皮がとても贅沢品だった戦争中、たった一足を、心をこめて作る切なさに打たれます。
戦争が激化する中、兵隊さんになるために田舎にかえっていったタスケさん。二度ともどらない時間を思わせる、最後の場面に、ぐっと心をつかまれます。
「魔女の宅急便」シリーズをはじめ楽しい作品をたくさん書いてきた児童文学作家・角野栄子さんが、今の子どもたちに読んでほしいと願って綴ったお話。一度しかない人生を、戦争とともに生きざるを得なかった人たちを描きます。
小さい女の子と靴屋のお兄さんの心の交流が描かれたかわいらしいお話でありながら、ずしんと心に残る「何か」を考えさせられる絵童話です。
(大和田佳世 絵本ナビライター)

1942年、東京。町の表通りに若い靴屋さんが越してきた。ひょろ長い体にぶあつい眼鏡をかけた靴屋のタスケさんは、いつも背中を丸めて古い靴を直している。「今は材料の革がないし、靴をあつらえるなんて贅沢は許されないしなあ。でも、こう見えても、腕はたしかなんだぞ」。小学一年生のわたしは放課後になると靴屋さんに行って、タスケさんの仕事を見るのが楽しみになった。わたしは、タスケさんのことが大好きだった。しかしまもなく戦争が激化し、タスケさんはお店を閉めて兵隊さんになるために田舎へ帰っていった。やがて、わたしはタスケさんのことを忘れていったーー。『魔女の宅急便』の作者・角野栄子が若い世代へ贈る、戦争のものがたり。
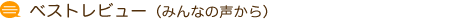
戦争が奪うもの。それはi命だけでなく平和な日常の小さな営みだ。赤い靴の話をわたしに語った時の「まだ平和な時だったな」が切なく響く。
戦争のむごたらしさ、悲惨さを詳細に克明に描いている訳では決してないが、ストーリーの中から湧き出てくるような悲しさがある。
角野さんが書かずにはいれれなかった作品なのだろうなあ。
(はなびやさん 50代・ママ 男の子16歳)
|