
高級店から回転寿司まで、代表的なおすし約320貫とネタ元の魚を写真で解説する、おすしの図鑑です。著者は、『からだにおいしい魚の便利帳』の著者のぼうずコンニャク 藤原昌?さん。二千種にも届こうとしている著者のおすしのデータベースから、比較的ポピュラーなもの、日本各地で実際に使われているものを選びました。同じ魚でも、皮霜、一般の握りなど、複数のすしダネを掲載しているものもあります。
さらに、すしダネには「超高」「高」「並」「安」というアイコンがつけているので、本書を片手におすし屋さんで安心して注文しやすくなっています。
本書はすしダネが320貫掲載してあるものの、バッグの中にいれてもっていけるハンディサイズになっています。ぜひ、本書と一緒にお寿司を召し上がってください。
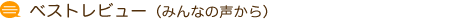
すし屋に行く機会はほぼないのですが、
肉よりも魚が好きで、魚釣りを始めた小3の息子。
かつ、難読漢字が得意で現在魚の名前をかなり覚えています。
そんなわけでこの本を手に取りましたが、
予想以上におもしろい。
食の歴史、寿司の歴史、魚の歴史から始まって、
寿司に関するあらゆることが書かれています。
鮭一つとっても、
トラウトサーモンとアトランティックサーモンと銀鮭と、
もうよくわからなくなってきているけど、分類がよくわかりました。
ニシンは、「鰊」で覚えていたけれど、
この本では「鯡」という字を当てている。
年貢をニシンで納めてもよいという藩があり、
この字があてられたとか。
ちなみに広辞苑では両方出ていました。
床伏(とこぶし)はアワビの子どもかと思っていたら、
違う種類だとわかったし、大人も知らないことばかり。
カツオは、春先の戻りガツオが脂が乗っててうまいと思っていたけれど、
江戸っ子は、秋の追いガツオが好きで「女房を質に入れても」追いガツオを食べたがったのだとか。
何がうまいってのは、つまり好みの問題なんですね。
寿司屋に行けなくても、スーパーで魚を買うにしても、
旬の時期や調理法を意識することができそう。
息子もかなり興味をもって読んでいます。
「寿司屋に連れてってくれ」と言われるのはつらいけど、
「釣ってきてくれ」で返そうと思う。
(Tamiさん 40代・ママ 男の子8歳)
|

