
ロシアに住むお金持ちの息子、ワーシャ。
彼は、毎日たっぷりお勉強をします。
お稽古にも一生懸命です。
お行儀も良くって、まったく申し分がありません。
彼は、『いい子』でした。
その、小さな絵具箱に出会うまでは――
色をまぜてみると、ワーシャは奇妙な音を聞きました。
「シューッ!」
今度はそれを塗ってみます。
「りりんりりん」
「がらんがらん」
なんと、色が音楽を奏でているではありませんか!
夢中になって絵を描いていくワーシャ。
「すごい絵が描けたよ!」
「家? お花? それはいったい、なんの絵だい?」
「音楽だよ!」
だれも、ワーシャの感動を理解してはくれませんでした。
大人になったワーシャは、絵とは無関係の道に進みます。
しかし、町中にあふれる色はいつも、ワーシャには美しく音を奏でているように聞こえるのです。
やっぱり絵描きになりたい!
そう決意したワーシャは、30歳にして画家を目指すことになります。
ワーシャ、彼の本名は、ワシリー・カンディンスキー。
これはのちに、『抽象画』というあたらしい芸術を生み出す、歴史的な芸術家の物語――。
抽象画って、何が描かれているのかよくわからない! そんな風に思う人も多いのではないでしょうか。
でも、もしカンディンスキーが、本当に『色を聴く』ことができたのだとしたら。
「カンディンスキーの絵画は、彼が色を使って奏でたひとつの音楽作品でもあるんだ」
本書を読んで、抽象画をそんなふうにとらえなおしてみたら、興味がわいてくるのでは。
実際に音が色として見えたり、色が音として聞こえたりといった感覚の交錯は「共感覚」と呼ばれ、現実に存在する現象なのだそうです。
カンディンスキーもまた、共感覚があったのではないかとする説もあるそう。
彼が聴いていた、色彩の歌う不思議な世界――。
それを、「ハリー・ポッター」シリーズの挿絵を手掛けたメアリー・グランプレが、どこか秘密めくファンタジーな光景として描きあげています。
形のないものを描こうと挑戦した、画家カンディンスキーの半生!
芸術の楽しみ方に、あたらしい視点を与えてくれる一冊です。
(堀井拓馬 小説家)

今から約100年前、だれも見たことがない新しい絵を目指し、形のないものをえがいた抽象画が誕生しました。周囲に流されず自分が信じた色と形を追いかけた抽象画の父・カンディンスキーの物語。コルデコット賞オナー作品。
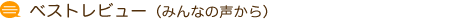
抽象画はよくわからないのですが、この絵本で、ちょっと親近感を持ちました。
絵の具から音楽を感じること、音楽を奏でるように画くこと、作品は感じるものになります。
親から望まれた生き方ではなく、規制の尺度で測られず、自分の本当にやりたいことにたどり着いたカンディンスキーを絵本から感じ取りました。
絵本の色調も内容も、カンディンスキー自身が解放されていくところをみごとに描いていると思います。
(ヒラP21さん 60代・パパ )
|