
「ぼくたちは、このまちで、であったんだ」
20世紀初頭、かつて世界の中心といわれたオスマン帝国が黄昏の時代を迎えていた。その都である〈海峡のまち〉で、トルコ伝統のマーブリング紙〈エブル〉をつくる職人の孫ハリルと日本人の貿易商の息子たつきが出会う。
「エブル」をつくる工房の家に生まれ育った少年ハリルは、周囲の友だちは新設された学校へ行っているのに、工房の親方である祖父のもとで下働きする毎日。一方、日本からやってきた貿易商の息子たつきは、異国の不慣れな土地で折り紙遊びで暇を持て余している。そんなふたりが海峡のまちで出会い、友情を深め、おたがいの感性をとおして、この街に生きる自分を見つめ直していく――。
アジアを描かせたら右に出る者はいない、『せかいいいちうつくしいぼくの村』の絵本作家・小林豊が絵を、その弟子でトルコをフィールドに取材執筆を行なう末澤寧史が物語と文を担当。師弟コンビが、20世紀初頭のイスタンブルを、生き生きと描く。
※手作業で表紙を加工しているため、表紙に貼ったシールや切手のデザイン、消印の位置が少しずつ異なります
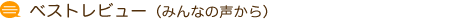
海峡の町に住む少年は、父の帰りを待ちながら、家の手伝いをして暮らしている。祖父の仕事を手伝う中、日本人の少年と交流し、祖父の仕事の素晴らしさを改めて知る。
2021年刊行。画面がセピア色なので、昔の話かと思った。そうでもないのかもしれないが。
トルコという遠い国で暮らす二人の少年の交流、まわりの人たちの温かさが嬉しい。人生は思い通りにならず、辛いことも多いが、このようにしてお互いに助け合いながら暮らしていったら、どうにかなる。
色のない画面のなかに、たくさんの色を感じ、市場の喧騒が聞こえ、海や香辛料の匂いもしてくるようだ。町の様子、建物の様子、にぎやかな場所やさびれた場所などの雰囲気も伝わってくる。
一度も行ったことがない場所なのに、昔から住んでいたような不思議な気分になった。
途中に本物のエブル(トルコの伝統工芸:墨流しアート)が挟まっている。作品の暗い色と、エブルの鮮やかな色が印象に残る。
表紙に切手が貼ってあったり、手作業で丁寧に作られた絵本。大切な思い出を届けてくれたような気がした。
(渡”邉恵’里’さん 40代・その他の方 )
|