
1967年の発売以来、日本中のあかちゃんに愛されつづけている絵本『いないいないばあ』。
何とこのたび、累計500万部突破というビッグニュースが届きました。これは日本の絵本では初めてのこと。
今やあかちゃん絵本の定番中の定番といってもいい一冊、『いないいないばあ』。
今回は改めてその魅力に迫ってみたいと思います。
●『いないいないばあ』のあゆみ
1967年 4月、『いいおかお』と同時刊行され、「松谷みよ子あかちゃんの本」シリーズがスタート。
1978年 全国学校図書館協議会「よい絵本」に選定。
1984年 累計100万部突破。
1993年 累計200万部突破。
2002年 累計300万部突破。
2007年 累計400万部突破。
2012年 累計500万部突破。
●『いないいないばあ』―実は…これが“初めて”!

現在では数々ある「いないいないばあ」絵本。日本の伝承あそびである「いないいないばあ」を絵本と結びつけたのはこの作品が初めてでした。

『いないいないばあ』が第1作となるシリーズ、「松谷みよ子あかちゃんの本」。「あかちゃん」向けの絵本であることを明記したのは、このシリーズが初めてでした。

2012年、翻訳絵本も含め、日本の絵本で初めて500万部を突破しました。
●普遍的な力をもつ絵本だと感じます。
それにしても、これだけ長く、多くのあかちゃんに読まれている『いないいないばあ』の魅力とは、どんなところにあるのでしょうか。刊行している出版社、童心社編集長の下園昌彦さんにお話をうかがいました。
───『いないいないばあ』がこのたび500万部を突破されたそうですね。本当にすごい記録です。おめでとうございます。
ありがとうございます。私も改めて驚いています。めまぐるしく世の中や人々の暮らしが変化していく中で、これだけ大切に読み続けられてきたことをとても嬉しく思っています。三世代、四世代にわたって読んでいる、という読者のお声をいただくこともあります。それぞれの世代でそれぞれの思い出になっている―この作品は普遍的な力を持っているのだとそのたびに実感します。
───私も子育ての中で『いないいないばあ』やシリーズ作品の『いいおかお』『もうねんね』をたくさん読みました。素敵な言葉と絵で、子どもとよい時間を過ごしたことを思い出します。
私も三人の娘たちと『いないいないばあ』を読んだ父親の一人です。娘たちが「ばあ」などと声を出して身体じゅうで喜んでくれたこと、その笑顔を見て、私も幸せな気持ちになったことを今でもはっきりと覚えています。ボロボロになった今でも大切にしている『いないいないばあ』が家にもあります。

───親子の思い出と一緒に大切に残しておきたい一冊ですね。
今回、改めてこの本を開きましたが、大人の私が思わず笑顔になってしまいました。
読むと笑顔になる、というのはこの作品の魅力をとてもよく表していると思います。この本を読んであかちゃんが笑顔になった、というお母さんの声もたくさんいただいてきました。
あかちゃんは、「いないいないばあ」あそびが大好きですよね。この絵本では、その楽しさをそのまま体験できるのです。「いないいない」「ばあ」という動きと、ページをめくる、という絵本の特性がぴったりあいました。

───なるほど。本という形と結びつけられたというのは一つの発見ですね。
では実際に『いないいないばあ』を見ながら少しお話をきかせてください。
はじめに出てくるのはにゃあにゃ、猫ですね。最初は手で顔をおおっていて、どんな顔なのか、どんな表情をしているのかわかりません。このときあかちゃんは顔が見えないので不安な気持ちになっています。それは「いないいないばあ」あそびでも同じですよね。そしてページをめくると……、とびっきりの笑顔のにゃあにゃが現れます。
───ページをめくる間にドキドキ感も募りますね。
それはとても大切な「間」ですよね。にゃあにゃがあかちゃんときちんと笑顔で向き合ってくれるので、あかちゃんは心から安心し、嬉しくて笑顔が弾けるのです。
───私は実際に読んでいて、「ほらね」などの優しい“お母さん”の言葉を読むのが心地よく、嬉しかったことを覚えています。
そうなんです。全体がやわらかな言葉で紡がれていますよね。そして、やわらかいというだけでなく、「ほらね」「ほらほら」などあかちゃんを絵本の世界へ誘い込み、「次はどうなるんだろう」とページをめくりたくなる言葉が散りばめられています。
───動物たちも何ともかわいらしく、好きです。
あかちゃんに伝わる絵なのだと思います。大きく描かれた顔やその表情、そしてしぐさもとても愛らしい。ぎゅっと体を小さく閉じている状態から、手を大きく広げた「ばあ」へ、その変化がいきいきと描かれていますね。
───二つの見開きでにゃあにゃの位置が違うのはなぜでしょうか?
これもこの『いないいないばあ』のすごいところなんです。あかちゃんは動くものに反応するので、「いないいない……」の後は、めくられていくページを目で追っています。めくって、にゃあにゃの絵をあかちゃんと一緒に見た後に「ばあ」と読むのがとても自然だと感じます。実験的に「ばあ」の絵と文字のページを左右逆にしたものを読んでみたことがあります。しかし「どうなるだろう…」とドキドキしながらページをめくる気持ちの流れが、間に文字が入ることで途切れてしまう感じがしました。
───この後もかわいい動物が次々に登場しますね。
次はくまちゃん、そしてねずみ…と「いないいないばあ」は続いていきます。とてもシンプルな構成ですが、だからこそあかちゃん自身が「次もこうなるだろう」と予想し、楽しむことができるのです。また、動物たちの「ばあ」の顔は、みんな満面の笑顔。笑顔で迎えられる喜びも繰り返し味わうことができるのです。読んでいる大人もあかちゃんの笑顔を見て幸せな気持ちになり、それがまたあかちゃんへと伝わる…人と人の心が響き合い、通じ合う、人生においてとても大切なことを味わえる時間だと思います。
───親子の間に絵本があることで気持ちが通う、ということですね。
あかちゃん絵本とはそういうものであってほしいと思います。松谷先生は子育てをする中で「あかちゃんのための絵本こそ、美しい日本語と最高の絵でなければならない」と感じ、『いないいないばあ』を生み出しました。日本にまだあかちゃん向けの絵本という概念がほとんどなかった時代です。あかちゃんが心から喜ぶものを、と試行錯誤を繰り返しながらの創作であったといいます。『いないいないばあ』は、生まれたばかりのあかちゃんを「この世界へようこそ!」と歓迎し、「あなたが生まれてきてくれて、本当に嬉しい」という深い喜びをあかちゃんに伝えています。私はこれこそ、当時作り手たちが追い求めた「あかちゃんの文学」なのだと思います。これからもこの『いないいないばあ』が、多くのあかちゃんに笑顔や安心を届けてくれることを願っています。
───いつの時代も生まれてくるあかちゃんへ届けたい大切なメッセージですね。
今日は『いないいないばあ』の魅力を再発見することができました。お話しいただき、ありがとうございました。
●特製フォトフレームのおまけ付!




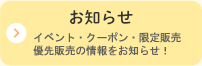
















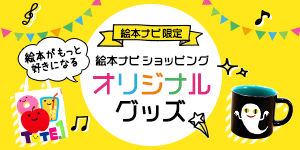 可愛い限定商品、ゾクゾク♪
可愛い限定商品、ゾクゾク♪ 








