SNSで話題、発売即重版! 入園・入学準備にもぴったりの一冊。
- 学べる
- 役立つ
絵本紹介
2025.02.19

うぅ、さむ~い!肩をすぼめながらふと見上げた桜の木には、枝の合間に小さくふくらんだつぼみが。道端の草に目をこらすとほんの少し顔を出している若葉が。まだコートやマフラーが手放せない真冬でも、寒さを堪えながら着実に春への準備をすすめる植物たち。その健気な姿にささやかな力をもらいます。
ご紹介するのは、春に顔を見せる植物たちが登場する絵本。
はるだ、はるだ! 冬眠から目を覚ました10ぴきのかえるが野原の仲間たちに元気にごあいさつ。『はるだ はるだよ! 10ぴきのかえる』はワクワクに満ちた春が明るいタッチで描かれた人気シリーズです。春の野原を観察してみるとタンポポ、ナズナ、レンゲにヨモギと草花でいっぱい! 身近な自然を描いた『いぬのにっちゃん はるとなつ』を読んだら本を片手に野原に出かけたくなっちゃう。
子ども自身が自分の家の庭をつくる『庭をつくろう!』やバラの栽培にチャレンジする『レイチェルのバラ』からはガーデニングの楽しさや喜びが伝わってきます。
陽だまりの中にいるような、あたたかな植物の絵本。待ち遠しい春はもうすぐ、ですね。

出版社からの内容紹介
困難に負けない勇気と希望、仲間と協力することの大切さを教えてくれる、読み聞かせにぴったりの「10ぴきのかえる」シリーズ。
冬の間、地面の下のふゆごもりハウスで眠っていた10ぴきのかえるが、目を覚ましました。
「はるだ、はるだ! ふゆごもりは おしまいだ!」
10ぴきのかえるは、ちょうちょうさんやかたつむりさん、どじょうじいさんに元気よく挨拶をします。野原へ行くと、たんぽぽやつくしんぼを見つけ、ふゆごもりから目を覚ました他のかえる達も出てきました。
みんなで、まだ寝ているかえるを起こそうと崖の下までいくと、穴の中から、おおいびきが聞こえてきました。ねぼすけがえるがいると思った10ぴきのかえるは、「はるだよ、はるだよ、おきなさい!」と声をかけますが、いくら呼んでも返事がありません……。すると、ぬうっとこちらを向いてきたのは……!?
この書籍を作った人
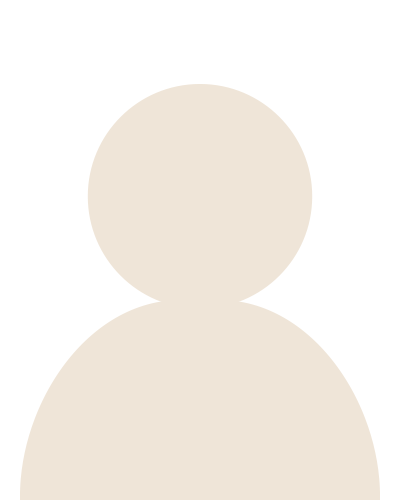
1938年、東京都生まれ。第1回日本童話会賞、詩集『山が近い日』(理論社)で第13回野間児童文芸賞推奨作品賞を受賞。主な作品に、「10ぴきのかえる」シリーズ(絵:仲川道子/PHP研究所)、「ころわん」シリーズ(絵:黒井健/ひさかたチャイルド)、『クリスマスにくつしたをさげるわけ』(絵:ふりやかよこ/教育画劇)『くっきーだあいすき』(絵:岩村和朗/金の星社)などがある。2019年死去。
この書籍を作った人
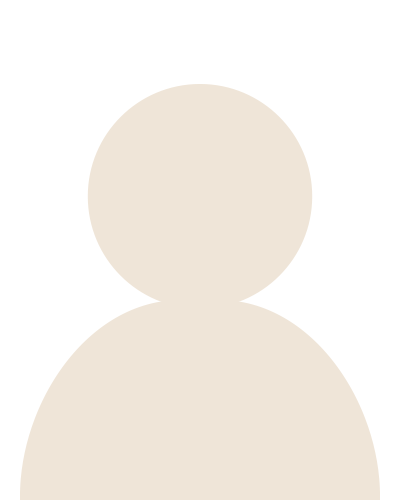
1948年、東京都生まれ。主な作品として、絵本に「パオちゃん」シリーズ、「10ぴきのかえる」シリーズ(ともにPHP研究所)、『ころちゃんはだんごむし』をはじめとする「かわいいむしのえほん」シリーズ(童心社)、紙芝居に「コッコおばさん」シリーズ(童心社)などがある。

みどころ
いちばんの仲良しだと思っていたのに。
ちょっとしたことがきっかけで、なんでこんなにも不安になってしまうのでしょう。
あんなに自信満々だったのに、突然、相手の考えていることがわからなくなって、胸がざわざわして落ち着かない。そうなると、ますますいろいろなことを考えすぎて・・・。
この絵本のネズミもそう。
友だちのテンの家にあそびにいくと、テンは留守でした。
ドアの貼り紙には「ともだちのうちにいくのでいえをるすにします」と書いてありました。だから、ネズミはなんの疑いもなく、いちばんの友だちの自分の家にテンが遊びにくるのだと思いました。
走って家に帰って、テンを待ちます。
でも、テンは姿を現しません。
その時、ネズミははじめてテンのいう「ともだち」は自分じゃないのかもしれないと傷つきます。じゃあ、だれがテンのいう友だちなんだろう。森に住むほかの仲間たちのことを想像しながら、ますます不安になるネズミ。ネズミはいてもたってもいられなくなってテンを探しにいくのです。
児童文学作家の岩瀬成子さんは、子どもの繊細な心の揺らぎを丁寧に汲み取った作品を数多く世に送り出しています。優しい言葉でネズミの気持ちを代弁してくれます。今回初の絵本作品となった中沢美帆さんが絵を担当。それぞれの生活を大切に営む動物たちとその暮らしを支える静かな森を温かく描いています。
ネズミは、テンに出会えたでしょうか。テンがいう「ともだち」は誰だったのでしょう。
読み終わったあと自然と優しい気持ちになり、友だちに会いたくなる素敵な絵本です。
この書籍を作った人

1950年、山口県生まれ。1977年、『朝はだんだん見えてくる』(理論社)でデビュー。同作品で日本児童文学者協会新人賞受賞。1992年、『「うそじゃないよ」と谷川くんはいった』(PHP研究所)で小学館文学賞、産経児童出版文化賞受賞。1995年、『ステゴザウルス』(マガジンハウス)、『迷い鳥とぶ』(理論社)の2作により、路傍の石文学賞受賞。2008年『そのぬくもりはきえない』(偕成社)で日本児童文学者協会賞受賞。2014年、『あたらしい子がきて』(岩崎書店)で野間児童文芸賞、JBBY賞、IBBYオナーリスト賞受賞。2015年、『きみは知らないほうがいい』(文研出版)で産経児童出版文化賞大賞受賞。2021年、『もうひとつの曲がり角』(講談社)で坪田譲治文学賞受賞。そのほかの作品に、『ともだちって だれのこと?』(佼成出版社)、『なみだひっこんでろ』(岩崎書店)、『ちょっとおんぶ』(講談社)、『ピース・ヴィレッジ』(偕成社)、『だれにもいえない』(毎日新聞社 )、『まつりちゃん』(理論社)などがある。
この書籍を作った人
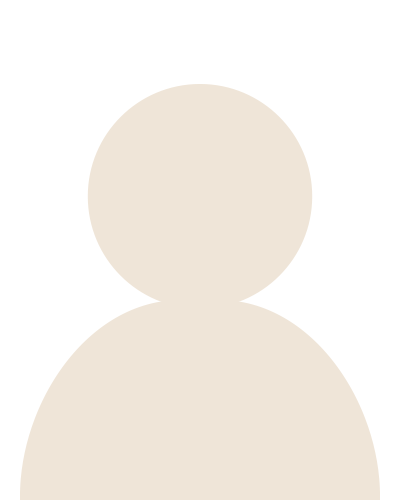
1926年、オランダ生まれ。アムステルダムのデザイン学校を卒業後、ロジャンコフスキーに憧れ、パリに移る。20代から現在に至るまで、精力的に絵を描きつづけている。おもな作品に『ソフィーのやさいばたけ』(BL出版)、『3びきのくま』(評論社)など。
この書籍を作った人

1970年、埼玉県生まれ。フランス語、英語の児童書を翻訳しながら、ときどきエッセイも書く。主な翻訳に『トラの じゅうたんに なりたかったトラ』(岩波書店)、『どうぶつに ふくを きせては いけません』(朔北社)、『うんちっち』(あすなろ書房)、『わにの なみだは うそなき なみだ』、『ふるい せんろの かたすみで』(ともにロクリン社)など。海外作家との交流も多く、「日本の神話えほん」シリーズ(岩﨑書店)では文を担当し、フランスの画家ポール・コックスと共同制作をした。登山と温泉が好き。
この書籍を作った人
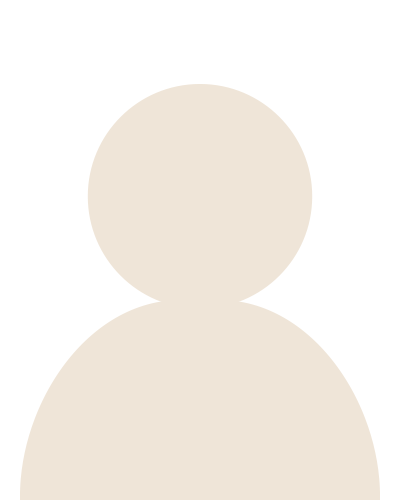
絵本・イラスト・立体造形作家。多摩美術大学グラフィックデザイン科卒。中森デザイン事務所を経て、フリーに。『色えんぴつでかわいい鳥たち』『どうぶつのかたち練習帳』(パイ インターナショナル)、『どうぶつえんに いきましょう』『ぼくと小さなポポフ』(教育画劇)など著作多数。

みどころ
おにぎりの定番具材梅干し。
見るだけで、口の中が酸っぱくなって、ヨダレが出てきて、
食べると、大人も子どももお年寄りも、みんなしわくちゃな顔になる、
日本人に最も身近な食材です。
でも、梅干しがどうやってできるか、知らない人も多いと思います。
そんな時には、この絵本。
梅の花が咲いて、小さな実ができ、塩漬けされて、天日干しされて、漬けられて、
立派な梅干しになるまでを「うめぼしさん、うめぼしさん」と語りかけるような文章で
教えてくれます。
文章を彩る絵は、どこか懐かしさを感じる、和風のタッチ。
小さな実のときは母親に守られている赤ちゃんのような幼い表情が
次第に若者のようなハリのあるヤンチャ顔になり、
おひさまとにらめっこをして少しずつしわが増え、
最後は優しい成熟した梅干しになる…。
ましませつこさんの描く、梅干したちは、
どこか人間のような親しみと愛嬌が感じられます。
中でも特にオススメなのは色っぽいシソの葉姉さんの登場で、
ぽっと赤くなる初心な梅干したち。
妙に色っぽいシソの葉姉さんの流し目もみどころです。
この書籍を作った人
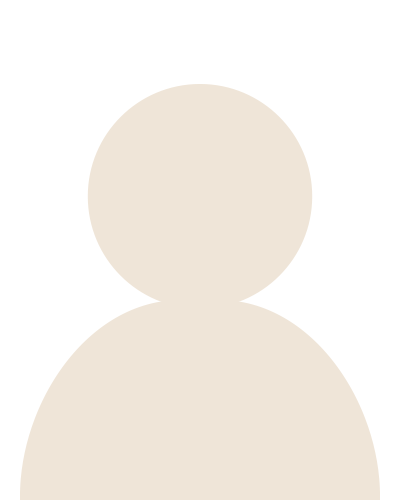
1937年、山形県鶴岡市に生まれる。女子美術大学図案科卒業。広告デザインの仕事にたずさわった後、子どもの本の世界に入る。日本の伝統的な色彩や形の美しさと、現代的なセンスが調和した優しい画風で、ファンが多い。主な絵本に『ママ だいすき』(まど・みちお文)『とと けっこう よがあけた』(こばやし えみこ案)『あがりめさがりめ』(いずれもこぐま社)など多数。
この書籍を作った人
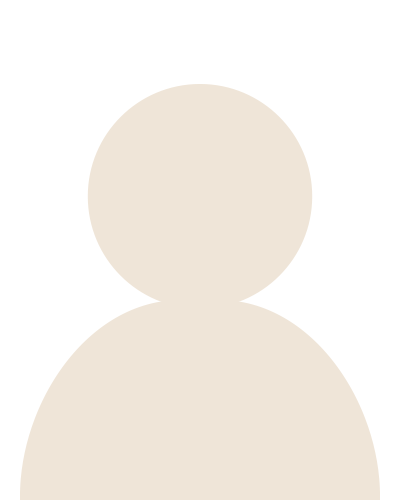
〈1915-2013年〉フランス・パリでスペイン人の両親のもとに生まれる。1935年に渡米し、1939年にエマ・G・スターン作の児童文学の挿絵でデビュー。以来、多くの作品で高い評価を得る。2013年7月、惜しまれながら97歳で亡くなる。
この書籍を作った人
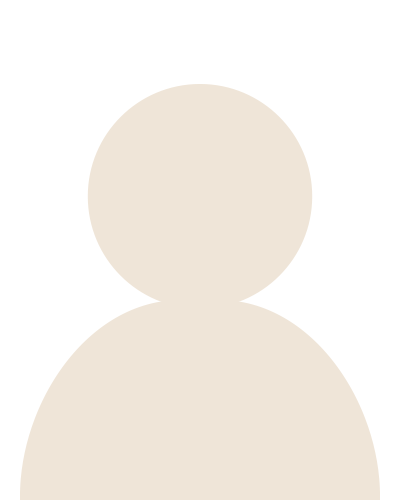
1896年岩手県花巻市に生まれる。盛岡高等農林学校農芸化学科卒業。十代の頃から短歌を書き始め、その後、農業研究家、農村指導者として活動しつつ文芸の道を志ざし、詩・童話へとその領域を広げながら創作を続けた。生前に刊行された詩集に『春と修羅』、童話集『注文の多い料理店』がある。彼の作品の殆どは没後に高く評価され多数の作品が刊行された。また、何度も全集が刊行された。1933年に37歳で病没。主な作品に『銀河鉄道の夜』『風の又三郎』『ポラーノの広場』『注文の多い料理店』『どんぐりと山猫』『よだかの星』『雪渡り』『やまなし』『セロひきのゴーシュ』他多数。
この書籍を作った人
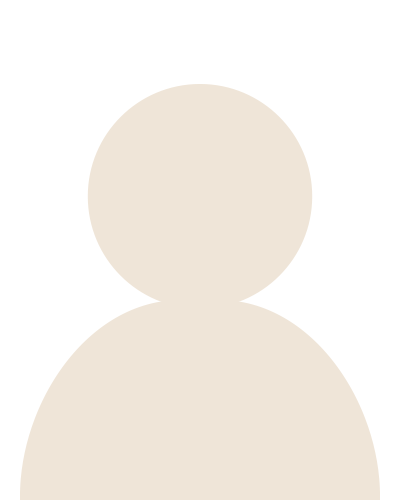
1942年、イギリスに生まれる。父親は建築家、母親は舞台装飾家という恵まれた家庭で育つ。幼い頃から絵が好きで、絵を描くこと、お話をつくることは彼女の楽しみで、4歳のときにビアトリクス・ポターの影響を受けてつくった初めての本は現在も残っている。ケント州のメイドストーン美術学校で学び、絵本作家のブライアン・ワイルドスミスに師事した。これまでに、グリムやアンデルセン童話の挿絵を中心に最近は創作絵本も手がける。イギリス・ケント州在住。
文/竹原雅子 編集/木村春子
