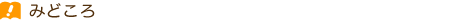
とある夜。
池のほとりに建つ、一軒の家。
ひとりの男の子が、その家に住むおじいちゃんを訪ねます。
ちいさな池のわきを行き、彼が家に辿り着くまで、あと、ほんの数十秒。
「ああ、やっとついたよ。おじいちゃんの家」
最初に男の子が発する、そのひと言よりもあと、最後のページまでこの絵本に台詞はありません。
あるのはただ、ところどころに記された、ちいさなオノマトペだけ。
鹿が口をつける池の水音。
獲物をとらえようと待ちかまえるカエルの鳴き声。
遠くを走る列車の汽笛。
群青の濃淡で表現される夜の空気のあちらこちらに、そんな”音”たちがちいさく立ち現れます。
池とほとり全体を俯瞰する構図は、流れるようにそのなかの一部分へとフォーカスし、ふと立ち止まり、あるいは顔を上げ、最後には飛び立つフクロウの後を追うように展開してゆきます。
オノマトペと鳥の目を通してながめているかのような構図によって、一見するととても動的な場面の連続に思われるのに、なぜかこの作品には、息の音を立てるのすらはばかられるほどの静けさが満ち満ちています。
そのうえ、劇的な動きの生まれる瞬間にだけ、この絵本からはオノマトペすら消えて、そこに真の静寂を描き出します。
それは大きな魚が水面を撫でるように泳ぎ去る瞬間であり、あるいはカエルが空を飛ぶ蛍をその長い舌でとらえる瞬間であり、フクロウが獲物を狙って爪を立てる瞬間です。
読者はとある奇妙な感覚を味わいます。
その瞬間絵本のなかで、夜を満たす静寂が、しん、と厚くなるのです。
なんの変哲もない夜の、ほんのわずかな時間。
本来は目にも耳にも入らないような、ささやかなできごと。
そんな小さな世界をながめていると、なぜでしょう、今この瞬間にも世界は息づき、命は巡っているのだという、そんな大きなことにまで想いをはせてしまいます。
静寂を聴くという、不思議な体験を味わってみてください。
(堀井拓馬 小説家)

男の子が池のほとりを歩いています。もうすぐおじいさんの家につくところです。もうすっかり日がくれて、空には月が輝いています。リリリ、リリリ。虫が鳴いています。遠くからは列車の汽笛。池に浮かぶハスの葉にはカエルがいます。シカの親子も水を飲みにきているようです。ほんの数十秒のあいだにおこる小さなドラマの数々。そこにひろがるゆたかな世界。ページをめくることが一つの体験だということが感じられる絵本です。
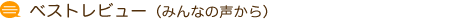
夏の夜、男の子がおじいちゃんの家へと池のほとりを歩いています。すぐそこに見える家までの道、さまざまな音が聞こえてきます。ゆっくりとページをめくりながら娘に読み聞かせました。
「あ!この虫いまも外で鳴いてるよね!」「ほたるはカエルにたべられちゃうの?」など音だけの絵本に夢中になっている様子でした。
たむらしげるさんのあとがきもとても素敵です。
(ouchijikanさん 40代・ママ )
|