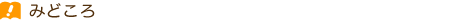
お父さんとお母さんが旅先で行方不明になってしまい、ひとりでしょんぼりしていた象の男の子。そこへやって来てくれたのが、「ぼくのおじさん」。彼を預かるため、迎えに来てくれたのです。
顔にはしわがたくさん、動き過ぎると体がぎしぎしするおじさんは、とても年老いているのだけれど、素敵なお庭を見せてくれたり、お話をしてくれたり、服を着れるだけ着て笑わせてくれたり。楽しいことをいっぱい知っている素敵なおじさんのおかげで、「ぼくとおじさん」の心の距離はだんだんと縮まっていったのです。そんな時、嬉しいお知らせが届き……。
ちょっぴり切ない展開から始まるこのお話。だけど、そこはやっぱりローベルなのです。二人のエピソードを、1章ずつ丁寧に積み重ねていきながら、読者はその世界にどんどん惹きこまれていきます。何より、鼻を使ってコミュニケーションをとる二人の姿がユーモラスで、とっても愛らしくもあり。おじさんの家の、暮らしぶりが伝わってくる背景も素敵です。心にじんわり染みてくる、親子とはまた違った魅力のある物語。
どんな状況にあっても、悲しい出来事に直面していたとしても、優しく包み込んでくれる人がきっといる。手をさしのべて、見守ってくれる人がきっといる。ローベルの子どもたちへの一貫した優しい眼差しや、強い思いが伝わってくる1冊です。
(磯崎園子 絵本ナビ編集長)

両親が行方不明になった象の男の子をなぐさめに、年とったおじさんが訪ねてきました。楽しいことをいっぱい知っている、すてきなおじさん!
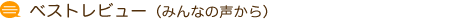
家族以外の誰かの存在って貴重だ。
「おじさん」って、その誰かに成り得るし、割とお話にしやすいようだ。
そのものずばり、「ぼくのおじさん」という題のお話がいくつかある。
ひとつは、ジャック・タチ監督の「ぼくの伯父さん」。
もうひとつは、北杜夫の「ぼくのおじさん」。
どちらのおじさんも、駄目人間として大人社会からは冷遇され、でも子供からは慕われる人間として描かれる。
・・・この2つの話から、おじさんって、駄目人間ばかりなのかと思ってしまうが、いやいやそんなことはない。
アーノルド・ローベルは「がまくんとかえるくんシリーズ」で有名だが、寧ろわたしは彼の「ぼくのおじさん」という作品が1番好きだ。
主人公のぼくは、ある日船の事故で両親をなくしてしまう。失意の彼の前に現れたのが、おじさんというわけ。おじさんは、きのはっぱよりも、はまべのすなつぶよりも、そらのほしよりもしわが多いおじいさんでもある。そして、孤独という点では、ぼくと同じ立場だ。
これは、そんな二人が心を通わせていく過程の静かな日々を描いたお話なのだ。
ぼくの緊張をときほぐしてやるために、電車の窓から見える電柱を数える話や、ランプに住み着いているくもの願いを叶えるために真っ暗な中で食事をする話、二人の関係を象徴するようなおじさんの作ったお話、おじさん流の気分が沈んだ時の対処の仕方の話・・・などなど。一つ一つのエピソードが、しみじみと心に残る。
最後の結末は、ぼくにとっては幸せであるはずだけれど、どこか物悲しくもあるのは、おじさんにとってぼくと一緒に過ごした日々は幸せであったという別れの辛さを表す。
年齢を超えた心の交流というとフィリパ・ピアスの「トムは真夜中の庭で」を思いだす。しかし、あちらは、過去の小さかったおばあさんとの交流であるということが違う。
絵本という限られたページ数で、ファンタジーという手法を使わずにおじいさんと子どもの心の交流を真正面から描いたという点で、とても心に残る1冊。
悲しい話ではないにも関わらず、読むたびになぜか涙が出てくる不思議な1冊。
誰か、映画化してくれないかな、と密かに思っていたりもする。
息子に読んであげられるようになるのは、まだまだ先の話だなぁ。
(のきこさん 30代・ママ 男の子6か月)
|