
江戸期の庶民の生活と心根を描く、「鶴見村もの」の集大成・書き下ろし長編作
おらあぶきだ。のろまでよう。
でも、ぶきだけんどぶきなりに、
たんせいこめりゃいいんだ。
江戸時代の終わりごろ――。
千太郎は、わずか七歳で、奉公に出されることになった。 奉公先は、鶴見村(いまの神奈川県横浜市鶴見区)の建具屋「建喜」。 まだ友だちと遊んでいたいさかりの、千太郎には、 建具職人になろうだなんて気は、さらさらない。
だが、先に奉公に来ていた姉、おこうにはげまされたり、 建喜の職人たちとのふれあいのなかで、いつしか自分も、 腕のよい建具職人になりたい、と思うようになる。
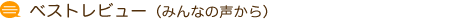
2010年読書感想文コンクール高学年の部課題図書。
江戸時代の終わりごろの建具屋(家の戸などを作るところ)が舞台ですが、
主人公は7歳にして奉公に出された千太郎、
先に10歳で奉公始めた姉のおこうの様子も描かれますから、
子どもたちには共感してもらえそうですね。
どちらも奉公とはいっても、男女で仕事は全然違います。
おこうは、職人さんたちの仕事を垣間見ながらも、家事手伝いに働きどおしです。
千太郎も、幼いとは言っても、手厳しく仕事をしつけられます。
その中で二人は、出会う人々との関わりを通して、
しっかりと成長していきます。
それぞれの立場で、懸命に生きる姿に拍手を送りたい気分です。
また、職人技も随所に出てきますから、そのあたりもたくさんの知識が得られると思います。
木の香り、加工の音などがリアルで、光景がよくわかります。
家の一部分とはいえ、このような工程を経ている、と知ることで、
物作りの奥深さも体感できそうです。
大人の視点からすれば、まだ幼い子どもに属する千太郎やおこうに対する、
たくさんの登場人物の接し方に目が行ってしまいました。
(レイラさん 40代・ママ 男の子16歳、男の子14歳)
|

