
日和(ひより)は、家が嫌いだった。
日和にとって家は、いつも緊張し、気をつかわなければならない場所だった。
日和は、妹の紅子が怖かった。
紅子は母にとっての女王様で、妹の機嫌を損ねれば、母に疎まれることになるから。
そして日和は、いつも祈っていた。
いつか、母が自分を愛してくれるようになる、そんな日を信じて──。
疎まれ、嫌われ、それでもなお母に愛されたいと願う日和。
家族がばらばらになってしまうことを恐れて、妻と娘の歪な関係から目をそらしつづける父。
そして、なんとかして我が子を愛そうともがき、しかし叶わずに苦悩する、母の愛子。
すれすれの均衡でなんとか家族の形を保っていた日和たちだったが、ある日、愛子の誕生日にその均衡を崩す事件が起きる。
「母は、娘を愛することもできず、捨てることもできなかった。だけど、あたしはちがう──」
『糸子の体重計』や『空へ』、青少年読書感想文全国コンクールの課題図書に選出された『二日月』、『チキン!』など、今もっとも注目される児童文学作家いとうみくがあらたに描くテーマは、”子どもを愛することのできない母親”。
もしこの物語が、日和ただひとりを主人公にしたものだったら──
もしこの物語が、愛子のことをただ「娘を憎むいじわるな母」として描いていたら──
もしそうであったなら、この切なさも、やりきれなさも、いくぶんかは軽かったろうと思います。
しかしこの物語では、中学一年生の日和はもちろん、その母親である愛子も、また悩み、戦い、もがく主人公のひとりなのです。
「あの子を抱くと、苦しかった。お母さんってすりよってきたとき、ぞっとしたこともある」
どうして我が子を愛することができないのだろう。
母親として大切な何かが欠けているのだろうか。
一方で、日和の妹である紅子のことは、自然と愛することのできた愛子。
紅子のことを愛する愛子の母としての言葉を読むたびに、「どうして紅子だけ」、「どうして日和のことは」という日和の悲しみがまざまざと思い起こされ、読者の胸を貫きます。
どうしても娘を愛することができない母親という衝撃的なテーマを、欠片の容赦もなく、そしてどこまでも真摯に描き切った一冊。
大人でも決して心穏やかには向き合うことのできない深刻な物語ですが、同時に、それを児童文学として届けようという試みに、子どもたちの強さや感受性に対する著者の深い信頼がうかがえます。
「家族が家族というだけで無条件に相手を愛し、理解しあえるものだとおしつけるのも、ちがうと思う──」
家族とはなにか。
母とはなにか。
傷つけ合いながらもなんとか家族であろうともがく日和たちが、苦悩の末にたどり着いた結論とは──?
子を持ちそして母を持つ、すべての人に届けたい、家族のあり方にあたらしい光を当てる衝撃的な一冊です。
(堀井拓馬 小説家)

どんなに願ったって、祈ったって、母はあたしを好きにはならない
あたしは、まだ母に愛されたいと思っている。
いつか母は、あたしを愛してくれると信じている。
そんなことは無理だとわかっていても、あたしはあたしの深いところで、いまも願っている。
カーネーションは、聖母マリアが、処刑されたキリストのために流した涙から咲いた……という伝承のある花。
そして、母の日に贈る、母性の象徴としての花でもある。
しかし、花言葉は色によって異なる。
母への愛、純粋な愛、そして軽蔑、拒絶、失望…。
児童文学の新風・いとうみくが描く、愛を知らない娘・日和(ひより)の物語。
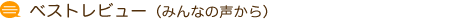
子どもが育つ条件として、無条件の愛情という言葉がある。自分の子どもだけら愛せる。愛さなくてはいけないというのは、ある種呪縛のようなものかもしれないと思った。
読み終わってから、時間が経って、『白雪姫』の継母は実母だったという話を思い出した。昔話の時代なら、娘を愛せない母も愛子ほど苦しむこともなかったのでは。
人の心の中のすべての感情に、理由があるわけでもないのだろう。愛子は、自分が日和を愛せない理由を探ろうとするが、探れば探るほど苦しくなるように思った。自分の中に、理由のつかない感情が存在することの息苦しさではないだろうか。
重たい話だが、日和の周りに、桃吾・一喜・柚希など日和を暖かく見守る存在がいることに救われる。
家族のあり様は、一様ではなく、端から見たら不可思議なこともあるように思う。
心ざわつく話だが、不思議にこの家族の決着のつけ方には納得ができた。
(はなびやさん 50代・ママ 男の子18歳)
|