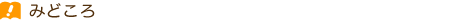
富安陽子さんの文、松成真理子さんの絵で贈る、あの世とこの世のあわいを描く不思議さに満ちたおはなし絵本。
まだ寒さの残る3月。
「わたし」はひとり、コソコソ、カサカサと落ち葉をふみながら、林のなかの尾根道をあるいていました。
どれほど歩いたのか、ふいに木立が途切れて、深い谷があらわれ、のぞきおろした「わたし」は、あっと息をのみます。
その谷は、満開の桜にうめつくされ、あかりを灯したようにピンクに輝いていました。
谷から聞こえてくる歌声があります。
「さくら やなぁ
さくら とてぇ
さくら ゆえぇ
さくら ちらすや かぜまかせぇ」
どうやら歌っているのは人ではなくオニたちのようです。
でも、本当に、彼らはオニなのでしょうか……。
山あいに突如あらわれたさくらの谷。
誘われるように「わたし」は谷へおり、オニたちとごちそうを食べ、かくれんぼをして遊び……ふいに気づくと、何もかも消えてしまっている……。
でも、さくらの谷もあの歌声も、目の前から消えてしまっただけで、この世のどこかにあるにちがいない……そう信じたくなります。
子どもが物心ついたときから、皆きっと心のどこかで不思議でたまらないと思いながらも、するっと手から抜けていくようにつかまえにくい、生と死のあわいへの思い。
たとえば、目の前から消えてしまったあの人やこの人は、本当にいなくなってしまったのでしょうか。
「人の存在、不存在」の真実をこのようにあざやかに見せられるとは思いもしない驚きと感動です。
富安陽子さんの歌と、松成真理子さんが描く、幻想的な桜の谷の光景をどうぞあじわってください。
(大和田佳世 絵本ナビライター)

 
かつて、わたしが一度だけ行ったことのあるふしぎな谷のお話です。
まだ山が枯れ木におおわれる春の手前、林の中の尾根道を歩いていたわたしは、のぞきこんだ谷を見ておどろきました。そこだけが満開の桜にうめつくされていたのです。
聞こえてくる歌声にさそわれてくだっていくと、谷底で花見をしていたのは、色とりどりの鬼たちでした。鬼なのに、ちっともおそろしいという気がしません。まねかれるまま、わたしは花見にくわわります。目の前のごちそうは、子どもだったころ、運動会の日のお重箱に母がつめてくれたのとそっくりです。
「かくれんぼするもの、このツノとまれ」
ふいに、一ぴきの鬼がとなえると、鬼たちはたがいのツノにつかまって長い行列になりました。列の最後の鬼のツノにつかまったわたしは、かくれんぼの鬼をすることになります。わたしは、林の中をかけまわってさがすのですが、なかなか鬼たちをみつけることができません。
そのうちに、だんだんふしぎな気持ちになってきました。わたしがおいかけているのは、ほんとうに鬼なのでしょうか。だって、いま、あの木のうしろにかくれたのは、わたしのおばあちゃんのようでした。こっちの木のかげには、おかあさんが。そこの木のうらには、おとうさんがかくれました。それは、みんな、みんな、もうこの世をさってしまった人たちなのでした。
でも、そうか。みんな、ここにいたのか。桜の谷であそんでいたのか──。
そうわたしが思ったとき、風がふきわたり、谷じゅうの桜がいっせいに花びらをちらします。
気がつくと、わたしはひとりぽつんと雑木林の中に立っていました。満開の桜はきえていましたが、ヤマザクラの枝さきに、大きくふくらんだ花のつぼみが見えました。どこかで、あの鬼たちの歌声が聞こえるようでした。
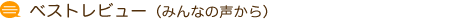
私の勝手な想像ですが、主人公の「わたし」は、もしかして、嫌なことがあって落ち込んでいたのでしょうか?
そんな時に遭遇した、さくらの谷の鬼たち。
さくらの谷は桜が満開で、お花見をしている色とりどりの鬼たちは、「わたし」を快く迎え入れてくれました。
「わたし」はすぐに打ち解けて、一緒にかくれんぼをするまでになりました。
けれど、かくれんぼの鬼となった「わたし」が木々を通して見る彼らの顔は、懐かしい顔ばかり。
もしかして、「わたし」の落ち込んだ心がかつての人たちを呼んだのでしょうか。
そうして、彼らとの触れ合いで元気になった「わたし」は、またきっと会えるからと、谷を後にしたのではないかと思いました。
春の始まりにふさわしい、幻想的な絵本でした。
(めむたんさん 40代・ママ 男の子20歳)
|