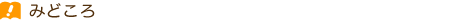
「『にっき』ってなに?」
「起こったことを書いておくんだよ。でも、ひいじいちゃんは、読むことも書くこともできなかった。だからマッチ箱にその日の思い出を入れることにしたのさ。」
本屋と骨董屋を営むひいじいちゃんが、遠方から会いにきたひ孫に、昔の話をします。
それは、あるイタリア移民家族の物語。
わずか38ページの絵本に味わい深い映画のようなエッセンスが詰まっています。
暖房どころか床もないイタリアの貧しい家で、オリーブの「種」をなめて空腹をがまんした少年時代。
アメリカに働きに行った父さんから、送られてきた「写真」のこと。
干ばつで食べ物ができなかった年、父さんを頼って、母さんと4人の姉さんとアメリカへ渡ったこと。着いてすぐ缶詰工場で働いたこと・・・(船で拾った「ヘアピン」、魚を缶に詰めるときの「骨」)。
1つずつ小さなマッチ箱にしまっていた思い出を、1つずつ(種、写真、ヘアピン、骨など)取り出しながら幼い少女に話してきかせます。
作者のポール・フライシュマンは、カリフォルニア生まれのカリフォルニア育ち。著名な児童文学作家シド・フライシュマンの息子です。アメリカの児童文学で最も権威あるニューベリー賞を親子そろって受賞しています(現在までで親子受賞は唯一)。
ほら話や冒険物の作風が魅力のシド・フライシュマンと違い、息子のポール・フライシュマンは多彩な手法のなかに、哲学的な心をこめた作品群が魅力。絵本に『ウエズレ―の国』『おとうさんの庭』、創作物語に『種をまく人』『風をつむぐ少年』『わたしの生まれた部屋』などがあります。
『わたしの生まれた部屋』は19世紀から20世紀にかけてのアメリカ・オハイオ州にある小さな村が舞台で、一人のおばあさんが自分の一生を語るという形式が『マッチ箱日記』と似ているかもしれません。
現代アメリカを代表する児童文学作家ポール・フラシュマンの文章世界をぜひ味わってみてください。
絵は、ロシア生まれ、アメリカ在住のイラストレーター、バグラム・イバトゥーリン。
『おとうさんの庭』でポール・フライシュマンとコンビを組んでいますが、絵のタッチは驚くほど違うんです。本作では、セピア色の写真のように古い情景を再現しつつ、人物の表情をこまやかに描いています。二つともスケール感のある美しい大型絵本なので見比べるのもおすすめ。表紙の“レトロなマッチ箱”に心ひかれたらまずはこちらからどうぞ。
ポール・フライシュマンの絵本は子どもも大人も楽しめますが、もしかしたら年配者のほうがぐっときてしまう・・・そんな味わいがあるかもしれません。
(大和田佳世 絵本ナビライター)

イタリアから移民としてアメリカにわたった少年は、働きに働き、思い出をマッチ箱に残してゆく。
きびしい暮らしのなかで、生きる支えとなったマッチ箱日記。
やがて少年は文字を覚え……。
少年の目を通して、移民の暮らしと困難な時代をあざやかに切り取った秀作。
マッチ箱日記をひとつひとつ開けながら、ひいじいちゃんが、ひ孫に自分の半生を語る、という形で物語は進みます。
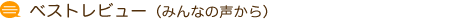
どうして子どもって小さなものを宝もののようにして集めたがるのだろう。
小さくなった匂いつきの消しゴム。きらきらひかるスーパーボール。遊園地の半券。鉄腕アトムのシール。ちびた青い色鉛筆。小指の爪ほどの貝殻。そのほか。そのほか。
机の引き出しの奥深くにそっとしまって、でもいつの間にかなくなってしまう、宝もの。
もしかしたら、それは思い出だからかもしれない。
誰にも渡したくない、けれどいつか誰かにそっと話したいような。
イタリアで生まれた少年は貧しい生活をおくっている。時には食事さえとれないことがあって、そんな時にはオリーブの種をなめることもあった。
小さくなったオリーブの種。それが少年の最初の「思い出」。
父親がアメリカに出稼ぎに行った時、少年はまだ赤ん坊だった。少年が知っている父親の顔は一枚の写真。
それが少年の二番めの「思い出」。
そして、少年たち一家は父親を追ってアメリカに移住することになる。
ナポリの町で見つけたのは、マッチ箱。
字も書けない少年は、その中に「思い出」のものを入れることにした。少年の、いわば日記。
ナポリでは初めて見た瓶入りの飲み物の王冠をいれた。
アメリカに着くまでの苦難。アメリカでの迫害。
けれど、少年はめげることはなかった。
マッチ箱の日記にはさまざまな思い出が詰め込まれていく。
魚の骨。新聞の切れ端。折れた歯。初めて見た野球のチケット。
やがて、少年は字を覚え、印刷工になっていく。
マッチ箱の日記はもう終わったけれど、別の方法で日々を綴っていく。
それは、本屋になること。「読んだらその時のことを思い出せる」から。
今ではすっかりおじいさんになった少年がひ孫の少女に語りかける人生。
たくさんのマッチ箱は、一つひとつは小さいけれど、少年の「思い出」がうんとつまっている。
生きていくことは、そのことを誰かに伝えていくこと。それは未来の自分でもあり、自分から続く人々だ。
「日記」とは、そのためのものともいえる。
精密な筆と温かな色調のこの絵本もまた、「日記」のようにして誰かに読まれつづけるだろう。
(夏の雨さん 50代・パパ )
|